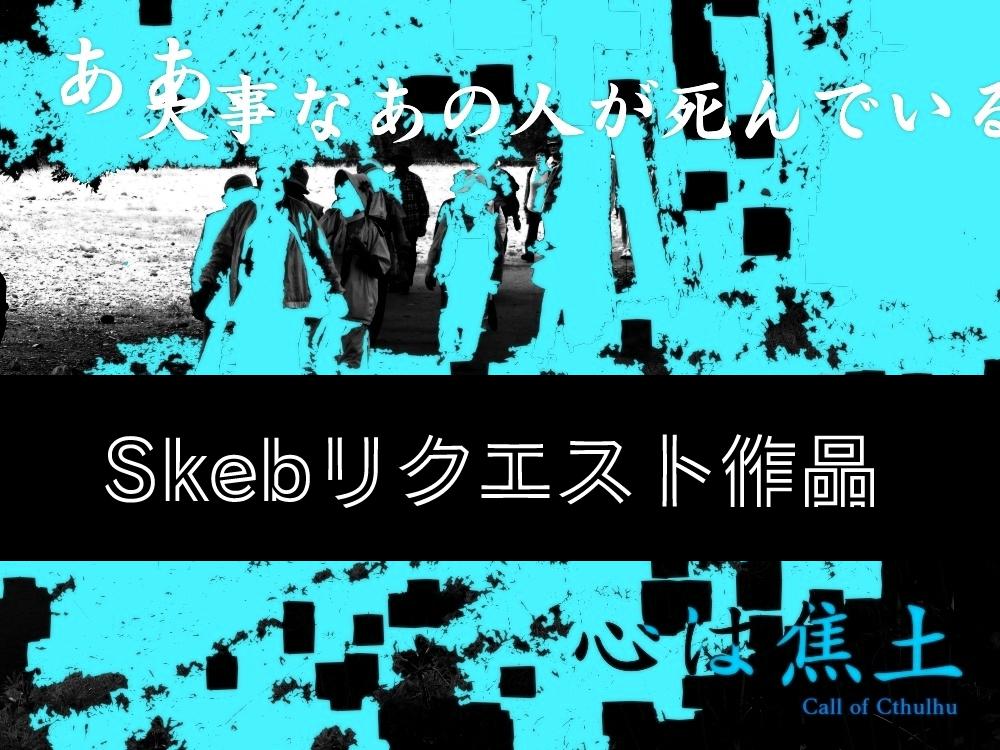▼シナリオ本編はこちら

また、今回は私がKPをした卓の探索者さんではないため、設定周りはかなり捏造&捏造捏造しています。あくまでも二次創作ということを踏まえてお読みください。
特殊組織所属の重継続2人、焦土エンドCロスト
敦賀くん→記者
火原くん→実家がヤクザ
付き合ってないけどお互いまんざらでもないって感じなんだって!し、死んでる…
『花信風』
0.
「選択が間違ってたらどうする?」
聞きなれた声をきっかけに意識が浮上する。
笑い声、食器が重なる音。目の前にはハンバーグにフォークを入れている火原が居た。
「なんだって?」
敦賀は目を見開いた。
ロッジ風のテーブルとカウンター席には見覚えがある。数日前──いや、『次の日』、自分たちが行くレストランだ。
「選択って、あ、あの男の質問のこと?」
敦賀はせわしなく辺りを見回しながら、上ずった声を出した。自分の記憶では『3月11日』にあの男に捕まり、成す術なく巨大な何かを視たのが最期だった。そこには火原も居た。ずっと困難を乗り越えてきた二人で、しかしどうしようもなかったのだ。
「はあ?」
火原が怪訝そうにハンバーグを頬張った。
「これだよこれ。ステーキとハンバーグで、ハンバーグにしちゃったけどステーキのほうが美味かったかもっつってんの」
「ハンバーグ?」
言葉に釣られて視線を戻せば、ちょうど一口大になったハンバーグがまた皿から火原の口へ運ばれていくところだった。
「ステーキのはずだ」
「あん?」
「ステーキだった、頼んだの」
「いやハンバーグにしただろ、二人でさ」
敦賀の手元にはじゅうじゅうと美味しそうな音を立てているハンバーグがあった。
1.
火原は叫び声をあげながら走っていた。あの男が呼び出した巨大で悍ましい何かから逃げようとしていた。
足になにかが引っかかり、その拍子に盛大に転んでしまった。ごろごろと斜面を転がり、打撲とは別の鋭い痛みが体中に走った。ようやく止まった頃には手も顔も足も小さな切り傷だらけだった。
火原は荒い呼吸のまま自分が落ちてきた方向を見上げる。
巨大な何かは影も形もなく、代わりにいつの間にか周囲は山であった。斜面は見たこともないキラキラとしたガラスのような花をつけた低木で覆いつくされており、火原が転がってきた軌道がそのまま、粉々になった花の破片の道を作っていた。体にできた無数の切り傷は、どうやらこの花びらで切ってしまったらしい。
「どこだここ」
また時間が飛んだのだろうか。火原は立ち上がる。
だが見たこともない山の中──少なくとも、3月中に訪れた場所ではなさそうだった。
「今何月何日……いやそれより楽也だ!」
自分と一緒に居たはずの相棒を探すため、多少よろめきながらも再び歩き始めた。木々が風に揺れる音や鳥のさえずりなど、山はのどかな音に満ちている。それに混じって、微かな人間の話し声が耳に届いた。
「楽也……?」
片方はよくよく聞き覚えのある声だった。
もう一人のほうは、わからない。
声のする方へ慎重に近づいてみると、小川が流れる少し開けた広場で、敦賀が誰かと座って話していた。
例の妙な花の木に隠れながら様子を距離を詰める。
広めの公園にあるような、木製のテーブルと長椅子。敦賀は自分と違って身綺麗な状態で、向かいに座っている人物は──、
「な、なんだ……」
向かいに座っている人物はフードを目深に被っているせいで顔こそ見えなかったが、袖からは手の代わりに細長い触手が出ていて、テーブルの上の大きな肉を握ったり離したりしていた。その肉というのも、肉らしく見えるというだけで、実際は人間の腹だけ切り取って目玉を乗せたような肌色の奇妙な物体だった。敦賀はそれを当然のようにフォークで刺しながら、目の前の相手に何事かを話していた。
「楽也っ!」
思わず茂みから飛び出すと、敦賀はこれ以上ないくらいに驚いたようだった。
「火原?なんで……あっ!」
相棒は猫のように飛び上がり、火原にぶつかる勢いで席から離れた。まるで「今おかしいことに気づいた」ように。
「なん…さっきまで君とレストランに、あのロッジの、でもハンバーグで、」
「あれを俺だと思ったのか?」
火原がフードの存在を指差すと、再度短く悲鳴が上がった。
2.
火原だと思った者は火原ではなく。
ハンバーグだと思った物はハンバーグではなく。
だったら死んだのも勘違いであればよいのだが、未だにその確信はなかった。
小川のせせらぎが場違いに綺麗な音を奏でている。
敦賀は隣の火原に顔を向けて、お互い目配せで頷いた。フードを被った何かは相変わらず肌色の肉塊を握ったり離したりしている。
「あの…さっきはすみません、人違いをしてしまって」
「ああ?お前マジか」
「黙って」
頷いたものの、普通に話しかけるとは思ってなかったのか火原が素っ頓狂な声を出した。敦賀は短くそれを制して目の前の異形に意識を集中した。
もしかしたらどこかで会ったかもしれない。
あるいは例の組織の蔵書かなにかで読んだかもしれない。
記憶を掘り起こそうとしても思考が霧散してわからないが、ただ長年の経験から、あれも今まで出会った悍ましい何かと変わらないことは理解した。
理解した上で、意思疎通を図れるのか確認したいのが二人の総意だ。
「僕たちいろいろありまして、今自分たちがどうなっているのかも此処がどこなのかもわからないんです。もっと言うなら世界がどうなっているのかも……もし良ければ教えてほしいのですが」
フードに覆われた頭がゆっくりと敦賀たちのほうへ向く。見てはいけないような予感と、礼に欠く後ろめたさで、半端に視線をずらした。
「おいっ!」
火原に脇腹を突かれた。
いつの間にか異形が小川を指している。
敦賀が慌てて小川を覗き込むと、ちょうど盆に乗った小さな盃が流れてきたところだった。拾えということかと思い、とりあえず手に取ったが、何も反応はない。
「あの、これ……」
おずおずと異形に盃を渡そうとした瞬間、みるみるうちに盃に香しい液体が満ちた。そしておよそそれ自身が受け止められる量の3倍は溢れ続けて敦賀の手を濡らした。
「うわ、うわ、うわ!」
「早く渡せよ!」
「受け取ってもらえないんだって!」
敦賀が手をびちょびちょにしている間も、異形は何もしなかった。それどころか、フードの向きからしてもうこちらを見てすらいないようだった。
「あの!僕たちどうすれば──」
敦賀は精一杯大きな声を出した。その途端、ブツンと視界が途切れた。
あの何度も味わった強制的に『飛ばされる』感覚。
だが、同時に初めて味わう妙な浮遊感もあった。
どすんと地面に落ちた、気がした。
「ああっ!」
火原もそうだったのだろう、すぐ近くでうめき声がした。
「いてぇ!コンクリ!?街!?」
喚き声で自分がコンクリートの地面に倒れていることに気づく。周囲の景色には見覚えがあった。自分の家のすぐ近所だ。
「戻ってきたみたい…?」
敦賀は火原を助け起こして歩道の端に寄り、ポケットからスマホを取り出した。
「火原……」
まだキョロキョロしている火原に画面を見せる。
『3月1日』。
3.
3月1日に何をしていたかといえば、正直覚えていない。
つまりやることがなかったかいつも通りの日だったのだろう。
火原は自分のスマホを漁ってみたがこれといって記録はなかった。敦賀も同様だった。
「まあGPSの履歴でどこに居たかはわかったけど、フツーに家。あとコンビニ」
「僕も職場だなあ……」
例の男に捕まるまで自分たちは数回過去に飛んでいた。どういう理屈かはわからないが、おそらくあの男のせいだろうとは思う。
今は平和そのもので、見慣れた街並みを横目に二人して敦賀の家に向かっていた。
「アイツに会うのは3月11日だ。だいぶ猶予があるな」
「でもあそこにあったトラクターを見たのはもっと前だよ」
「あー、そうだっけ」
「それに順当に飛ぶわけじゃないし、次またいきなり11日かも」
「だとしても」
今度は別のことができるじゃんと明るい声で言った。敦賀を励ますつもりだったのに、自分に言い聞かせているようで少しバツが悪くなった。
火原は話題を変えて先ほど見た奇妙な存在の話をしようとした。だが敦賀が立ち止まったせいで会話が途切れた。
「どうした?」
「布団が干してある……」
敦賀の視線の先はちょうど彼の部屋がある場所だった。確かにベランダに布団が干されている。
「マメだな。天日干し?」
「知らない布団」
「は?」
「知らない布団」
一瞬沈黙が流れ、二人で弾けるように走り出した。玄関前まで来て鍵を差そうとしてもまったく合わない。敦賀が鍵の上下を逆さにしたりなんだりしてる後ろで、火原はインターホンを押した。
「おい誰も…」
「表札が違うぞ」
敦賀が愕然とした表情で顔をあげた。アルミプレートの表札には『駿河』と書かれていた。
「スルガ?僕はツルガだ」
「わぁってるよ」
やがてドアが開いて、見知らぬ青年が顔を出した。青年は如何にも迷惑そうな顔で「セールスですか?」とだけ発した。
「いや!取材ッス!最近このへんでスリが多発してんスよねえ!」
火原はそう言って敦賀を小突いた。ハッとした表情が一瞬こちらに向いた。
「そ、そうなんです。このあたりの治安について住民の方からご意見伺ってまして。ここには何年ほどお住まいに?」
こうなると本業は強いものである。火原は内心感心しながら、取材と聞いてちょっと頬を緩ませた青年を見た。
「大学入ってからなので3年ほどですかね。てかスリってホントですか?そんなに?」
「3年…。ああ、日中の子連れの方を中心に狙われているそうです。だからお兄さんが実際に遭われたことはないかと思いますが、噂とか変な人を見たとかありませんか?」
「噂かあ…」
青年は真面目に考え始めた。3年住んでいるという情報を得た以上、特に付き合う意味もないが急に帰るわけにもいかない。火原はちょっと敦賀を見た。敦賀もちょっと視線を返してきた。上手い落としどころを考えているのだろう。
「ああ!」
青年が声をあげた。
「スリじゃないですけど、ほら、こっからわりと近い博物館!玄関にエグい落書きされて3月いっぱいは臨時閉館ってニュースやってませんでした?」
「は、博物館て、国立博物館?」
「そうそう。企画展も中止だって」
4.
敦賀は火原を連れて近所のカフェに身を寄せた。
つい数分前、火原の家の表札が『三原』になっていたのを確認したばかりだ。
「ミハラねぇ」
「ちょっと違うよね。さっきから」
「博物館もやってねぇし。ゾウの像を買うこともないので安心ですネ」
「その代わりいきなりホームレスだけど」
「あそこは?」
オレンジジュースを啜りながら、火原が指をふよふよと動かした。
「ダメだね……どうやっても繋がらない。そもそもそんな組織自体ないんじゃないかな」
「ないってこたぁないだろ」
「じゃあ実家あったのかよ」
「ない……」
火原は手あたり次第親族に電話をかけて全滅していた。どれも『三原家の誰か』に繋がってしまうのだ。一方で敦賀も、所属している例の抗神組織には一回も繋がらずじまいだった。
「たぶん戸籍もないよ、僕たち」
「あ~~もう!なんで資料やデータベースが必要なときに丸ごとなくなるかねぇ!こんなの絶対いつものやつだろ!」
「いつものやつ……だけど」
少し整理したくなって紙ナプキンを一枚拝借する。長方形を三つ書き、一番左端に「3/14~3/9」と記入した。続けて真ん中の箱には山、右端には3/1。火原はそれを見つめてウウンと唸った。
「『山以前』と『山以後』では違う?」
「そうそう」
敦賀は左端から右端まで矢印を引きながら頷いた。
「最初、いくらタイムトリップしても少なくとも僕たちの知ってる世界ではあった。でも山のあとは世界自体が違う。3月1日だから紛らわしいけど、『別件』な気がする」
「左のは前後移動だけど右のは横移動って感じだ」
「え?…ああ」
一瞬遅れて火原の言葉を理解する。
「飛ばされる方向って話ね。ここが僕たちの世界とよく似た並行世界だったら『横移動』かもね。だとしたらもう時間は飛ばないか」
「そしたら……」
火原がぐいと伸びをして窓の外を見やった。猫の目のような彼の瞳が眩しそうに細くなった。
「もう安アパートでも借りて一緒に住むかぁ」
その言葉に、敦賀は自分が3年くらい黙った気がしたが、実際は1秒にも満たない空白だった。
「どういう意味?」
「どういう意味って何?」
「いや、同棲……」
「じゃあずっと野宿スか」
「あ、ああ、そう、それは困るな」
「安いとこなら身元審査緩いし、住所さえ出来たら仕事はできる」
「うん」
敦賀は半端な返事と共に火原を見た。火原は最初片眉をあげていたが、やがて自分の発言に気づいたのか、段々となんとも言えない表情になった。
「さ、最終手段な、最終手段」
火原がひらひらと手を振った。
5.
火原はすっかりジュースを飲みほしてしまった。
そんなことに引っかかりやがって、この状況じゃあ健全な提案だろう──と思うものの、なら不健全な場合もあるのか?と自問自答しかけて首を振った。
「腰を据えるにしても、もう少し足掻いてからにしよう」
敦賀の声に「トーゼンだ」とぶっきらぼうに返した。
「元の世界に戻る方法か、少なくともあの山にもう一度行く方法を知りたい」
先にほじくったくせに、敦賀はもう気にしてないようだった。
「山か……あのフード野郎に気を取られてたけどあそこ自体なんか変だったよな」
「変だけど綺麗だったよ」
「肌色のぶよぶよもか?」
火原の問いかけに敦賀は顔をしかめた。この男はあれをアツアツのハンバーグだと思い込んでいたのだという。だが実際は、人の腹をちぎって断面を縫合したような代物で、少なくともひき肉を整形したというよりは、大きな一個の塊である印象が強かった。
「“ショゴス”かな」
比較的一般的な──一般的であっていいはずがないのだが──怪異の名前を挙げる。敦賀がすかさず否定した。
「あれはもっと大きいだろう。それに肌色じゃない」
「こんなに正解でも不正解でも嬉しくないことってあるんだな」
火原はぼやきながらスマホを取り出した。『肌色 肉 怪物』と指を動かせば、意外なことにそれらしい候補がいくつか出てきた。
「ぬっぺふほふ、似てる~」
真っ先に表示されたのは肉の塊に手足が生えた妖怪だった。色味といい質感といいかなり似ている。
「でもデカそうだな。顔もあるし」
「そんなんで出てきたら苦労しな──」
「あ!」
敦賀の言葉をかき消すほどの大声が出た。じろりと刺さる周囲の視線に軽く礼をしつつ敦賀にスマホを渡すと、彼もまた小さく声を漏らした。
検索結果の1ページ目からさほど遠くないサジェストに、『太歳』と題された肌色のぶよぶよとした塊の写真を掲載しているページがあったのだ。
「タイサイ、中国に伝わる不老不死をもたらす謎の生き物……え、でも写真載ってる。てか僕これテレビで見たことある」
「普通にいるのか、じゃあ。それくらいいるか」
「いやあ、」
記憶では目玉はついてなかったけどね、と敦賀は首を傾げた。
「太歳は土の中を移動する妖怪とも、肉によく似た不思議な菌類とも言われる。別名ニクレイシバ。……だとさ」
「ニクレイシバ?」
敦賀が聞き返すので火原は『肉霊芝』という単語を指差してやった。
「ああ、ニクレイシね」
常識だとでもいうように訂正が入る。
「『霊芝』は、現実ではマンネンタケの一種なんだけど、伝説上では不老不死の薬の原料になる魔法のキノコだね。特定の種類かはともかく、中国ではそういった類のものは蓬莱という仙人が住む異界に生えてるっていうのが通説で」
「おいおいちょっと待て、なんでそんな詳しいんだ?伝説キノコ博士か?」
思わず水を差すと、敦賀はほんの少し表情を曇らせた。
「キノコに詳しいわけじゃない。異界や禁足地のことを調べたときに芋づる式に知ったんだ。つまり……神隠しとか、行方不明とか、そういう関係の」
皆まで言うまでもなく、かつて行方不明だった彼の兄に関することだった。火原は思い至らなかった自分に内心舌打ちした。
「なるほどな」
普通に暮らしてた人間が急にいなくなる、そしていなくなった人間は実は異界に居た、という話は古今東西を問わずどこにでもある。居なくなった経緯にキナ臭さも加わるとなれば敦賀がそのあたりも調べているのは当然だろう。桃源郷や蓬莱、崑崙あたりの異界の名前なら火原でも聞いたことがある。
「じゃああそこは中国?」
「さあ?でもあれが伝説上の太歳なら可能性はあるんじゃない?」
火原は黙った。パスポートもない状態で中国に行くことがどれほど難しいことか、敦賀だってわかっていることだった。それも香港や上海ならともかく、中国の異界が目的地とあればどうにかして飛行機に乗れたところで、である。
ぼんやり目線を窓に向けた。ここから見える大きな運動公園の中にある、ガラスと鉄柱でできた建造物がキラキラと陽光を反射していて、うららかな春の日を強調しているようだった。
「外、さっきからなんかあるの?」
敦賀の問いに火原は首を振った。
「なんかキラキラしてていい景色だから、現実逃避」
「ああ、植物園ね」
「植物園なのか。確かに」
デカい温室みたいだなと火原は言った。
6.
仕方なく移動する。
見慣れた街並みはまだ少し肌寒いものの、薄曇りから差す春の日差しを受けて柔和な表情を浮かべている。
この何百回も歩いた街に自分の家だけないというのは、思いのほか堪える現実だった。相棒に殺された挙句、意図しない時間旅行をさせられるほど破壊的ではないが、現状も十分速やかに脱すべき異常事態ではあるだろう。ただ、あまりにも直前までが悲惨だったせいで『ここ』に落ち着くという選択肢が心の片隅に現れているだけだ。
敦賀は先ほどの火原の『失言』を思い返しながらあてもなく彷徨っていた。当人は先導する敦賀になんの疑問も持っていないらしく、自分に目的地があると思っている顔をしていた。
「これからどうする?」
だからこの問いかけに火原が目を丸くしたのは無理もないことだった。
「なんも考えてなかったのか?散歩?」
「そうだよ。糸口もないままカフェに何時間も居座ったほうがよかった?」
「おい…別に怒ったわけじゃねえよ」
後ろから聞こえた弱々しい声に思わず足を止めて振り返った。ピアス付きの眉がハの字に下がっているのが見えた。
「ごめ──」
しゃん。
敦賀の謝罪が奇妙な鈴の音によって遮られた。
しゃん、しゃんという大きな音が断続的に聞こえてくる。
ビルの間の細道に目をやれば、向こうの通りを黄色い服の男たちが列を成して歩いていくところだった。
長方形に切り取られた視界の中、鈴の音に合わせて読経じみた声をあげながら次々と黄色い影が通り過ぎる。敦賀は火原と共に慌てて細道を抜けその行列に迫った。
男たちは二人に目もくれず通り過ぎていく。
様相としては寒修行のようだが、服装は袈裟と着流しを合わせたような奇妙な黄色い服を着た者が大半だった。
「カルトだ」
火原が経験から来る率直な感想を述べる。敦賀も口には出さないものの同じ感想だった。
「話のわかるタイプだったりしないかな」
「なんの信徒なら安全?」
「イ…」
「違います!」
突如真横から怒鳴られ、敦賀と火原は飛び上がった。いつの間にか口ひげを生やした男が立っていた。長髪を頭頂で団子にしており、結び目に黄色い布を巻いている。首から下も例の黄一色の奇妙な服だったが、髭と髪型が合わさって、これが古代中国の『袍』に一番近いのではないかと気が付いた。
男は狂人特有の生き生きとした瞳で敦賀を見た。
「しかし、そのような存在を御存知である上で、そしてお困りの様子。もしよろしければ私共の修行場へいらしてお話をお聞かせ願えませんか!?」
一語ずつはっきり丁寧に発音する男を見ながら、敦賀は火原と顔を見合わせ、数秒の間のあとに声を揃えて同意した。
少なくとも農場で単身儀式を行おうとしている男よりはマシだろうと思ったのだ。
「では、私に続いて列の先頭に!ご心配なく、私共は犠牲と知性を追求する者!いきなり殺人など犯しません!」
「順序立てて犯すことはあるのですか?」
「はい!」
7.
『黄金知性会』の修行場はだだっ広い古寺だった。『黄金知性会』というのは先の男たちが所属するカルト教団体の名前である。火原は敦賀と共に小汚い広間に通され、黄色い座布団の上に座った。その周りでは信者たちが好きな方向に座って念仏──に聞こえる呪詛かなにかだろうが──を唱えていた。
火原は自分でもびっくりするほど大人しかった。
道中も男の相手はほとんど敦賀に任せきりになってしまっていた。どうやら自分はあのとき『農場主』に迂闊な発言をしたことを想像以上に後悔しているらしいと、敦賀の横で意味のない自己分析をした。
「まずは私共のことを知っていただきたいと思います」
男は黄色い袖を翻しながら大げさなお辞儀をした。敦賀も「よろしくお願いいたします」と頭を下げた。火原も慌ててそれに倣った。
男は朗々と話し始めた。
「私共の信仰する神は、幽玄なる神域にて、賢き者に珠玉の知恵を与え、愚かなる者に破滅を与えます。もちろん身分・出身・家柄──なんと信仰も一切関係なし!条件さえクリアすればどなたでも神の知恵を賜るチャンスがあるのです!」
大音量の演説の背後で、部下と思しき信者二人がバッと大きな紙を広げた。
畳一畳はあろうかという巨大な和紙に、琥珀色のフード付きローブを着た長身の人型が描かれている。
「あっ!」
火原は思わず声を上げた。男の大きな目がこちらに向いた。
「御存知でしたか」
「い、いえ、詳しくは……。手が触手になってる奴…御方…スよね」
「その通り!」
指差しと共に肯定され、火原は曖昧な笑顔を浮かべた。
「この方の御名は『エメラルド・ラマ』あるいは『琥珀の長』!琥珀色のローブの下の御顔には黄色い一つ眼以外なにもなく、手や足は触手で出来ていらっしゃるそうです。そうです、というのはつまり……私共は未だにお会いできたことがないからなのですが」
なるほどと、敦賀がまったく自然に相槌を打った。
「みなさん随分修行してらっしゃるように見えますが、それでもお会いできたことが?」
はい、と悲しげに男は頷き、一人の老信者を前に呼んだ。老人は剃髪しており、右手がまるごと、左手は小指以外を残して何もなかった。
「重要なステップは二つ。まずお会いするために『大きな犠牲を支払うこと』。しかしこの大きな犠牲が具体的にどういうものかはわかりません。安武さん──このご老人は少しずつご自分の手を切り落としていますが、会えないままもう左小指しか残っておりません。あちらの百合子さんは──」
男は入口付近で念仏を唱えている中年女性を指した。
「五人兄弟だったのにもう一人っ子です」
女性は軽くお辞儀をした。
「……もしかして最低限のラインを探ってる?」
再び「その通り!」と声が上がる。相槌に困っている火原の横で、敦賀は顎に手を当ててなにやら考え事をしたあとこう切り出した。
「実現可能かどうかはさておき、これなら絶対に会えるという犠牲はありますか?例えば、世界ひとつとか」
ぴたりと、広間中の念仏が止まった。
信者の視線が敦賀に集まる。
男は大きな目を更に大きく見開いていた。
「それは……ええ、もちろん『世界ひとつ犠牲にした』ならば、偉大なるエメラルド・ラマにはお会いするに値するでしょう。しかし──『世界ひとつ犠牲にできる』ならば、その方は既に別の神の御力を借りていらっしゃるのでは?」
ニッと白い歯が覗く。広間のあちこちから笑い声が起こった。火原は敦賀の顔を横目で見て彼らに合わせて笑った。敦賀も笑顔を見せていた。
「すみません。気になってしまって」
「いえいえ、確かに生贄というのは多いほうが良いイメージがありますよね」
「ええ、それで──では二つ目のステップは?」
敦賀は容赦なく質問を投げかける。男は嬉しそうに人差し指を立てた。
「偉大なるエメラルド・ラマからの謎かけに正解することです」
「謎かけ」
火原と敦賀はほぼ同時に復唱した。その反応を気に入ったのか、男は一層饒舌になった。
「エメラルド・ラマにお会いできたとしても、無条件でお力を添えていただけるわけではありません。ご自身と相対するに相応しい賢者かどうかジャッジすることを望んでおられます」
「でもアンタたち──」
会ってないのになぜわかるんだと言おうとして敦賀に止められた。
「どんな謎かけなんですか」
「それがわかったら苦労しません。獅身人面の怪神スフィンクスのように決まった出題があるのなら別ですが、おそらくは毎回違うのでしょう。人を見ているのか、ご気分なのか、なんにせよ、過去問を解けばオーケーというものではないことはたしかです」
「ま、間違ったらどうなるんだ」
「破滅です。例外はございません」
火原の問いに真っ白な歯が答えた。
8.
エメラルド・ラマに認められた者はかの神によって願いを叶えられるという。
大方の人間はかの神が持つ人智を超えた知恵を望むだろう。
だがもっと具体的な願いでも構わない。
例えば、
「楽也っ!」
火原が半ば泣きそうな顔で敦賀の腕を掴んだ。あのカルト教団に見送られて街に帰ってくるまで、考えることが多すぎていつの間にか火原を無視していたようだ。敦賀は謝罪を述べて火原の顔を見つめ返した。大きな目の中にオレンジ色の夕日が反射していた。
「何か思いついたんなら言えよ!俺ら、なんでかあのエメラルド……ラ、ラマとかいうのに会ったんだろ?それっていいことだったんかな?悪いことか?」
「なんで会ったのかという点なら大体当たりがついてる。たぶん君が呼んだんだろう」
「俺が?」
わかりやすく目が丸くなる。対照的に敦賀は目を細めた。
「君が──答えたろ。あの男にさ」
目の前の友人が青ざめていくのを見て、敦賀は少しだけ後悔した。
「俺のせい?」
「君のせいじゃない。これは文字通りの意味だ、火原。君が『協力する』と答えたことによって男は僕たちを捕まえた。でも、裏を返せば君がそう言わなかったら、男はあの時点ではまだ事態を進められなかったんじゃないか、って思うんだ」
「だ、だから俺のせいって言いたいんだろ」
「男については、そう」
敦賀のストレートな物言いに、火原は拗ねることすら許されなかった。
「けど、エメラルド・ラマについては違う。君が『協力する』と答えた、男はなんらかの儀式をおこなった、何かが呼び出され世界が滅んだ、だからエメラルド・ラマに会った」
「世界ひとつ犠牲にしたら、ってやつ?でもそれなら一番実行者に近いのはアイツだ。俺はキッカケを作っただけで」
「そう、でも──」
君、助かりたいと思ったんじゃないのか。
敦賀はそう言った。
世界を滅ぼす引き金を引きながら助かりたいと思うのは矛盾だ。
だが、矛盾にならない場合もある。
「助かりたいという願いを叶えるために世界を滅ぼした、と思われたなら」
「で、でも!」
火原は一瞬絶句したが、それでもなお食い下がりたいようだった。
「じゃあお前が居る理由は?俺が世界を丸ごと生贄にしたイカレ野郎だってエメラルド・ラマに思われたんだったら、お前が生贄に入ってないのはおかしいだろ!」
「それ、僕に言わせるの」
敦賀は火原の顔すれすれまで近づいた。
先ほどまで夕日でいっぱいだった瞳が自分でいっぱいになる。
「何がだよ、わかってるなら言えよ」
不安げな声から漏れた吐息まで聞こえる距離だった。
「お前が僕のことを考えなかったわけないだろ」
敦賀がそう言うや否や、火原は飛び上がったかと思うほど後退した。どうせ『2人で』助かりたいと思ったに決まっているのに、この男は自分に指摘されるまですっかり忘れていたのだ。敦賀は距離を取ろうとする火原の腕を掴んで引き戻した。
「実際、僕は君が来るまでアレを視認すらできなかったわけだし、オマケだったんだろうな」
そこまで言って、眉間に力が入った。
そうとわかっていたらあんな風にでしゃばる真似はしなかった。
「どうした?」
掴みっぱなしの手の上に火原の手が重なった。
「オマケのくせに台無しにしたと思ってさ」
「あの…謎かけ?」
「そう。軽率だった。もっと考えて動くべきだった……」
敦賀の目は火原も夕焼けも見ておらず、後悔と怒りを以てここではないどこか遠くの景色を睨みつけていた。渡された盃が謎かけだったとしたら、自分は千載一遇のチャンスを逃したことになる。
小川を流れて来た盃。
どこから流れてきていたのか、どんな模様だったか、仔細はなにも覚えていない。いや、そもそも見ていなかった、と思う。
迂闊だった。
「あれってまだ続いてんのかな」
火原の言葉が思考をブツリと断った。
「何…?何だって?」
「ええ?お前が言ったやつだよ。謎かけ」
心配そうに重ねられていた手が、今度は容赦なく指を差してくる。
敦賀はそれでもよくわからなかった。
「何日までに答えればいいと思う?」
「いや、もうあれは──」
答えられなかっただろう。
声が少し掠れた。
「でも、破滅してねーじゃん」
「え?」
「謎かけに正解できなかったら破滅なんだろ。絶対。でも俺たちって破滅してないよな?それとも、破滅って家と戸籍がなくなるだけ?」
矢継ぎ早な火原の問いに敦賀はたった一言も返せなかった。言われてみれば、そうなのだ。破滅と認めるにはいくばくかの猶予を感じる状態である。
「でも盃をどうすればいいかわからなくて──」
今度は敦賀が意味もなく食い下がる番だった。肌色の粘菌じみた物体、美しい木々、小川のせせらぎ、盃を差した異形の指。
太陽がどんどんと落ちていく。
茜色の光を受けた火原の髪が琥珀に透けている。
「わからなくて?」
「いや、火原、僕は、勘違いしてたかも」
「だよな」
火原は安心したように笑った。
「正解すれば俺たちなんとかなるんだよな?元の世界に戻るか、家を建ててもらうかはさておき」
「そうだね」
あの場所で起きたこと全て含めて『謎かけ』なら、まだ自分たちは回答していない。
敦賀はようやく少し微笑んだ。
9.
3月2日。
火原はスマホを見た。昨日3月1日はネットカフェで一晩過ごし、今朝は3月2日になっている。やはり、ここでは普通に時が過ぎるようだ。
敦賀はまだ隣の個室で寝ている。見たわけではないが、眠りが浅かったせいで彼が一回も部屋を出入りしていないのは知っている。
あのあと、敦賀は多少──少なくとも疲れているから早めに寝ることを提案するくらいには
──元気になり、ネカフェを見つけるとさっさと二人分のチャージを済ませていた。
火原はというと、取ってもらった個室でしばらく備え付けのパソコンを触っていた。キーボード音で起きているのがバレそうだったので途中からはスマホに変えたが。
ようやく横になったのは明け方だった。
「ツァン高原……」
火原は数時間前まで調べていたページを開き直した。
ツァン高原という、チベットやモンゴルが位置する中央アジアにある呪われた高原。ここでは忌まわしい奇妙な民族が「黒い蓮」を栽培している──らしい。火原が今までの奇怪な経験から得た知識の一つだった。
それを洗い直しているのは「エメラルド・ラマ」という呼称に引っかかったからである。
ラマとはチベット語で「高僧」を意味する。
偶然とは考え難い。
結局、真偽不明の掲示板の書き込みやら怪しい個人サイトやらを転々としてたどり着いたのが「レン高原」という、やはり中央アジアに関連する高原だった。
レン高原はアジアの異界に在るとも夢の向こうに在るとも言われる譎詭変幻の領域であり、件のエメラルド・ラマ──琥珀の長が神殿を構えている場所でもある、という。そのレン高原が現実に染み出したのがツァン高原であり、ツァン高原からレン高原に行くには「黒い蓮」を使えばよい。
らしい。
世迷言と世迷言が繋がっただけの、奇天烈な情報だ。「らしい」とか「だそうだ」とか、そう思って然るべきである。
だが火原は、この情報に行きついたことで自分の中でもやもやしていた何かが言語化され始めていた。
あのエメラルド・ラマが居た世界は──
「わざとらしすぎんだよなあ」
ぽつりと呟くと同時に、隣の男がドアを開ける音がした。足音を頭の先で聞きながら目を上に向ける。ノックの音がして、半端にドアが開いた。
「起きてた?」
「ああ」
「寝てるかと思った。どうする?今日は……」
「賢い奴ってどんな奴?」
火原の問いは敦賀の眠そうな目をこじ開けた。
「賢い?ああ、謎かけを考えてた?」
「そんなところ」
敦賀はちょっと考えて、「相対するに相応しい賢者かどうか、でしょ」と言った。
『黄金知性会』の男の引用である。
「知識がある者って感じじゃないよね。まあ、博識な人は賢いけどさ。でもクイズ王を決めたいわけじゃない気がする」
「うん。『謎かけ』だしな」
「となると、限られた手札から答えを導ける人じゃないかな。挙一反三ともいうしね」
「なんだって?」
「一を挙ぐれば三を反す。四つのうち一つを教えてあげたら、残り三つを類推できる能力ってこと」
「わかった。孔子だ」
「賢いね」
敦賀は心底意外そうな顔をした。
こういうものは大体シェイクスピアか孔子なのだ。火原は1/2を当てただけだが、黙っていた。
「で、なんでそんなことを?」
出口に寄りかかる敦賀を横目に、火原は生返事をしながらここを出る支度をした。今調べたいのはチベットの冒涜的な領域ではなく、中国の古典に謳われた異境の数々だった。
10.
火原に引っ張られるようにして、敦賀は図書館へと足を運んでいた。
彼曰く、謎かけは誰でも解けるようになっているはずだという。
これは魔術や冒涜的な神話の知識がなくても、という意味だろう。
敦賀は談話OKのスペースにある窓際のテーブルにハンカチを置いた。場所取りできるような荷物はほとんどないのだ。火原は不用心にもスマホを置いていた。
「チベットやレン高原のほうは本当にいいの?」
「ああ。タイサイとかが載っているほうがいい」
「じゃあ中国の伝承とか古典文学になるかなあ」
二人して関係がありそうな本を片っ端から積み上げて、中国の異境に関する情報を拾っていった。敦賀にとっては昔ひととおり調べた伝説である。結局のところ、兄はそんな美しい場所には居なかったのだが。
「そういえば……」
敦賀はエメラルド・ラマが居た不思議な空間を思い出す。木がたくさん生えていたから山だと思っていたが、寒くもなければ澄んだ空気もなかった。では伝承に謳われるように花々の蕩けそうな香気が漂っていたかというと、それもなかった。
あそこに確実に在ったのは、目玉のついた肉塊と盃を運んできた小川と、透き通った花が咲く低木群だけだった。
火原は、それを『わざとらしい』と表現した。
「あった!」
本人の声が敦賀を思考の海から引き戻す。指差されたページを見れば、『瓊蘂』という言葉と共に美しい宝石で出来た赤い花の絵が描かれていた。
「後漢の張衡曰く、砕いて朝食にすれば不老不死になれるという神秘の花。生えている場所は美しく神秘的な、…な…」
「ロウエン、かな」
閬苑という字を見て、敦賀は呟いた。
閬苑は仙境──仙人が棲む場所という意味だ。幽明交わる異境そのものに使われる言葉ではあるが、そもそもは崑崙の山中にある『閬風』にある苑のことだ。
蓬莱にあるという太歳と、崑崙に生えるという瓊蘂。
「たしかに『わざとらしい』」
敦賀は火原を見た。
「蓬莱は中国の東の海、崑崙は中国の西の山というのが通説だ。もちろんこの謎めいた霊薬の正確な生産地なんてわからないけど、ただ、意図的に配置されてるなら一箇所を指してるわけじゃないんだと思う」
「中国の異境ってことが大事なんかな。小川は?流されてたのはコップ…盃か。あれも中国の伝承だったり?」
「そんな話は聞いたことがないけど……」
盃には液体が並々と満ちて一度止まり、敦賀がもたついていると中身が溢れ出した。それもまた数秒で止まった。酒が尽きない不思議な器の伝説は世界各地に見られるが、伝説を模しているにしては地味な量だ。
「チベットにはあるかな?あそこらへんは仏教と一緒に中国の文化が伝わってるから雰囲気が似てるけど、地理的にインドの影響も受けてるからちょっと独特なんだよね」
「こんな街の図書館にチベットの本は早々ないぞ」
「まあ、そうか…。一旦場所は置いておこうか。関係ない別の手がかりかもしれないし」
敦賀はそう言って、あの小川を思い出した。
小川はゆるやかにカーブを描いていて、そこまで深くはなさそうだった。美しく、川底が透けて見えていた。
小魚などはいなかったように思う。
なんとなく手元のメモ帳にスケッチ未満の小川を描いて消しゴムを滑らせた。盃を模すにしては大きすぎるが、止まった形で盃を描くのも違うように思ったのだ。
カーブが最も膨らむ縁に棒人間を加筆する。これは敦賀である。
エメラルド・ラマが指差したとき、盃はちょうど敦賀の目の前に流れてきたところだった。消しゴムを図の中の敦賀の前に滑らせた。
すぐ拾えたことを考えるに小川の流れはゆるやかだったのだろう。いやそもそも、盃は盆に乗せられていた。漂流物じゃない。拾うことを想定した形だ。趣は真逆だが回転寿司に近いような気がする。
メモ帳の端をちぎって消しゴムに乗せた。
紙片が盃、消しゴムが盆である。
「平泉」
敦賀の手元をぼんやり眺めていた火原が急に声をあげた。
「お、思い出した。俺これ平泉で見たことがある」
平泉とは、あの中尊寺金色堂の平泉だろうか。
そういえば火原は東北の生まれだった。
「ガキの頃、連れてかれたことあるんだよ。仙台から高速乗ればすぐだからさ。おふくろがめずらしく明るい色の着物を着てて、俺は手を引かれてた。兄貴もいたかな?親父はいなかった気がするけど、ええと」
「簡潔に」
「デカい庭に人が集まってて、川に盃が流れてた。皆和服だった。しかもあれ、貴族みたいな」
「狩衣とか十二単ってこと?」
それは、ついこの間見たものではないか。
企画展『日本の伝統文化』に嫌というほど出てきた展示だ。
「ああ、俺たちはまあただの観客だったけど、そいつらは盃が来たら、あの、『有明の…』とか言ってさ、歌、歌を詠むんだよ!雰囲気が全然違ったから気づかなかったけど、でも今考えたらすげー似てるぜ、これ。平泉の──」
毛越寺だ、と火原は言った。
毛越寺は中尊寺と並び世界遺産・平泉に含まれる著名な寺である。スマホで毛越寺の年中行事を調べれば、今までの自分たちの時間を嘲笑うかのように簡単に答えが出た。
「『曲水の宴』っていうらしい。平安時代に盛んに行われていた行事で、火原の言うとおり盃が流れてきたら歌を詠む。時代や場所によっては詠めなかったら酒を三杯飲むっていうルールもあったって」
「テキーラ・ショット・ゲームじゃねぇか」
「伝統的に『曲水の宴』が行われていたのは……さ、3月3日」
明日だ。
敦賀の動揺とは逆に、火原は納得いったという顔をした。
「回答のタイムリミットってわけ」
「大きな一歩かな。ここからどうつなげる?」
地名はたくさん出てきている。蓬莱、崑崙、平泉。
だがあくまで点として浮かび上がってきただけで、線で結ばれるかどうかもわからない。
そもそも、自分たちは『謎かけ』で何を聞かれているのだろうか?
「場所を特定してあそこに戻れたとして、なんて回答すればいい?」
「まあ、逆算するしかないだろな。今のところ、俺たちが『ちょっと考えれば』わかることしか出てきてないし、それはたぶん『わざと』だと思う。言っちまえばあそこにあったのは太歳じゃなくて黒い蓮でもよかったろうし、状況的にはむしろそれが自然だろ?でも太歳があった。『黒い蓮がある!じゃあチベットだ!飛行機乗ろう!』じゃあ奴(やっこ)さん的には面白くねぇわけだ」
「それじゃあまるで──」
あそこに戻ること自体が回答みたいじゃないか、と敦賀は言った。
11.
──ありゃいづがかつかアスガラミなっがら。
まだ十も越えない頃、遠縁の老人たちがそう話しているのを聞いたことがある。
幼い頭でなぜか自分のことだとわかった。
アスガラミは地元の方言で足手まといという意味だという。
袖絡みと書いてアスガラミと読む。
平泉に連れて行ってもらったときの火原は母の着物の端をずっと握っていて、まさに袖に絡んでいるようだったろう。
やはり自分のことだったのだ。
目の前の男にもそう思われる日が来るのだろうか。
「曲水の宴っていうのは中国発祥らしい」
余計な思考を打ち払うように火原は声を出した。
「そうだね。向こうでは流觴曲水と言うって。周代の頃からあったみたいだけど、文献として有名なのは『蘭亭序』に出てくる描写かな。これは晋代」
敦賀の返答と並行してスマホに指を滑らせる。
晋代は四世紀。平安時代より四、五世紀も前に大陸では定番行事だったらしい。
「オリジナルの『蘭亭序』は唐の王様が躍起になって探すほどだったんだってさ」
「唐?」
「うん?」
「いや──」
ちょうど中国の興亡史を見ていた火原のスマホには、七世紀から十世紀のところに『唐』と表示されている。
「平安時代と被ってるなって」
「ああ、そうだよ。当時唐は時代の最先端だったから、平安貴族は唐風の物をごっそり輸入して嗜んでたんだ。彫刻も書物も歌も──あ」
敦賀は急に言葉を切って顎に手を当てた。
「……関係ないかもしれないけど……、企画展に書いてたな。『源氏物語』も漢籍の引用が多くあって、清少納言の教養の高さを伺えると。特に白居易とか、唐代の詩を好んで──」
考えながら話しているせいか、いまいち言葉が途切れ途切れである。
火原はあえて黙っていた。
「漢詩には定番の比喩表現があるんだ。特に美しいものや素晴らしいものはこの世のものではないものに喩えられることが多い。蓮の花の美しさを仙女と言ったりね。だから、」
詩の中になら違う場所も同時に存在できる、と敦賀は結んだ。
白楽天に引っ張られでもしたか、極めて感傷的な言い回しだが要は『崑崙』『蓬莱』が同時に出てくる詩を探したいということだろう。
「漢詩なんて死ぬほどあるだろ。3000年の歴史だぞ」
「一回唐代に絞るさ。白居易だけでもいい」
「白居易は何本作ってんだよ」
「たぶん多くて100とか?」
敦賀は軽く言ってのけたが、ちょっとスマホを見たあとに真顔になった。
「3800本らしい」
「さ…え?」
「エメラルド・ラマに良心があるならこの線は違うか」
「そいつがエメラルド・ラマだったら自分の詩を全部読ませるかもな」
冗談のつもりだったが、万に一つ冗談ではない可能性もあることに気づいて口を閉じた。
敦賀もへの字口でこちらを見つめていたが、観念したようにため息をついた。
「全集持ってくる。そっちは白居易以外を調べて」
「唐代の、白居易以外の、有名どころだけな」
火原は丁寧に言い聞かせるように言った。
しかしこれも、すぐ後悔することになった。
唐詩というのは凄まじい量があるのだ。白居易だけで3800本作っているのだから当然ではあるが、有名どころだけに絞っても何冊も本が出ている。
しかもまだ日本で出版されているものしか見ておらず、本国の翻訳本には手を付けていない。
「李白、杜甫、杜牧、孟浩然…」
漢詩に明るくない自分でさえ聞き覚えのある詩人はみんなこの時代の生まれらしい。
向かいの敦賀は白居易の担当だが、険しい顔を見るに進捗は良くなさそうだった。
既に疲れ始めている指で力なくページをめくった。
「海、なんだ?」
読めない単語がタイトルになっている詩だった。
作者は李紳。さすがに知らない。
注釈には「海棠」でカイドウというタイトルだと書いてある。花の名前だそうだ。
漢詩にも花にも詳しくないせいでなんのイメージも湧いてこなかった。
「海辺の佳樹、奇彩を生じ……」
海邊佳樹生奇彩
知是仙山取得栽
瓊蘂籍中聞閬苑
紫芝圖上見蓬萊
淺深芳萼通宵換
委積紅英報曉開
寄語春園百花道
莫争顔色泛金杯
「ああっ!?」
凄まじい声が出た。
「瓊蘂籍中、閬苑に聞き、紫芝圖上、蓬萊に見る…」
指でなぞりながら何度も確かめる。確かに崑崙と蓬莱が出ている。それどころか、瓊蘂と、太歳そのものではないが霊芝にも言及されている。
敦賀が慌てて横に来て一緒に詩を眺めた。
「海棠の美しさを瓊蘂や霊芝の神秘性と並べているのか。最後は他の花に美しさを競うなと忠告して終わってる」
莫争顔色泛金杯の部分だろう。
注釈には『蘭亭序』の曲水の宴を踏まえての句だとある。
「これじゃねぇか」
「これだ」
二人で顔を見合わせた。
敦賀はページに食い入るように前かがみになり、一語一語確認するように読み上げた。
「詩にあるのは越州の海棠のことだって。越州は浙江省で…でも李紳自身は江蘇省の生まれだし他にも色んな所に赴任してるみたいだ。でもどこも今から行くのは厳しいよ」
火原は焦る敦賀の横顔を見ながらなんとなく詩を反芻していた。
彼の解説でようやく情景を掴んだからだろうか、フィルムカメラのように頭の中で勝手に景色が広がった。
詰所の屋上に登るかなにかして眼下の街を見下ろす。
軒が連なる遥か向こうに森があり、さらに向こうに海が広がっている。
森と砂浜の境目を縁どるように綺麗な紫の花が咲いている。花びらは大きく、少ない。花自体は紫の垂れ幕のような形だが、対照的なシュッとした葉が野暮ったさを切っているように見える。
遠くにあるはずなのに手が届きそうなほど近くに花が咲いている。
ああ、と火原は目を細めた。
これは、母の着物じゃないか。
自分は海棠を知らない。越州になにがあるのかも知らない。
母はあのとき菖蒲(あやめ)の着物を小さな花々が散らされた帯で締めていた。
袖にも裾にもたくさんの花が咲いていて、綺麗だった。
たくさんの花が──。
「楽也」
気づいたら敦賀の腕を強く掴んでいた。
「植物園だ。きっと海棠も咲いてる」
12.
図書館に長居しすぎたせいですっかり夜になっていた。
あと数十分もすれば日付が変わる。3月3日、曲水の宴がおこなわれる日。
植物園のガラスの壁も鉄柱も夜になれば青白く黙っているだけだった。昼間のきらめきがなくなるとこうも冷たく感じるものかと、敦賀は妙に落ち着いた気持ちで裏手に回った。
火原がいなければここにたどり着くことさえできなかったろう。
少なくとも二日では無理だった。
「開いた」
火原は慣れた手つきで施錠されたドアを破った。警備員に見つからないように二人で慎重に中に入る。一定の温度が保たれる温室の中は、人がいなくてもやや暑い。
夜の帳のせいで花々も彩度が落ちている。
物寂しいと思う。
「海棠ってどんな花?」
「背の低い桜みたいなやつらしい」
「はは、全然違った」
なにが、とは聞かなかった。きっと火原の中での話なんだろうと思った。
「ラベルは『ハナカイドウ』だと思う。外植えで4月開花だから温室内ならもう咲いてるんじゃないかな」
「会えたらなんて願う?」
「え?」
「エメラルド・ラマだよ。願い事、どうする?」
「もう正解した気になってるのか」
「今は海棠がなかった場合のこと考えたくねーの」
我が物顔で伸びている植物たちとは違い人間が歩くための道は狭い。必然的に前後に並んで歩くしかなく、敦賀は先を行く火原の頭しか見えなかった。
「元の世界に戻りたいけど、たぶん滅んでるからな」
「俺たちが世界の王様になろうか」
「滅んだほうの?それとも…」
聞き終わる前に火原が足を止めた。彼の明るく染めた髪越しに視線を先にやれば、円を描くように桜に似た低木の花が植えられていた。
薄紅色の鮮やかな花びらは真夜中でもよく見える。
光源がない場所なら瓊蘂とやらより綺麗なのではないだろうか。
「行こう」
知らないうちにそう言っていた。
「いいよ」
火原はちょっと笑って仕方ないという顔をしていた。問答を切り上げたことに少しの文句があるのだろう。
敦賀も気づいていないわけではないが、あまり聞きたくなかったのだ。
大事なことだとは、思うが。
13.
正直願い事なんてもうないんじゃないだろうか。
時ここに至り、という感じで、今更なにを願うんだろう。
もうみんな死んだようだし。
敦賀は元の世界に戻りたいそうだ。
巻き戻して、元通りにしてから戻れるものだろうか。
じゃあやり直せたとして、俺は正しい判断ができるのだろうか。
14.
輪の中心に入った瞬間、むせかえるほどの海棠の香りが肌にまとわりついて気を失った。
そう感じただけかもしれない。
気づいたら火原と一緒に小川のほとりに立っていた。
小洒落たウッドチェアにはフードを被った異形が澄まし顔で座っていた。実際に顔は見えないが、そんな雰囲気があるのである。
「どうも」
敦賀はお辞儀をした。火原はやはり怪訝そうな顔を浮かべた。
「エメラルド・ラマ様ですよね。あのときは知りませんでしたが、親切な方たちに会って教えてもらいました。またお会いできてうれしいです」
自分でも驚くべきことに本心七割といった感じだった。
「願い事を叶えてくれるってほんとスか」
火原が単刀直入に聞いた。
エメラルド・ラマはまったくごく自然に頷いた──まるで、最初からまともに会話できたといわんばかりに、自然な仕草だった。
こういった手合いのこういうところが嫌なのだ、と、きっと火原と同時に思った。
「話し合います!」
火原の宣言に、また自然な頷きが返ってきた。
「で、どうする?」
視線がこちらに向く。
「願い事ね。どんな規模までOKかわからないけど、元の世界に戻るなら世界を復元してもらってから戻りたいよね」
「それさ、時間は戻す?」
「え?」
「復元してもアイツに目をつけられてたら意味ないだろ」
火原の目に一抹の不安が混じる。正しい指摘だった。なんだかんだあったが、結局あの男の対処法はわかっていない。
「世界を復元してもらって、時間を戻して、アイツにはスルーされるように、いや他の人間で同じことされるかもしれないから、アイツだけ消すとか」
「山盛りすぎない?」
「じゃあ現状維持」
妙にはっきり言ってしまった。
火原の目が飛び出そうなほど丸くなった。
「いいの?」
声音が少し高い。
ああ、こいつ、戻りたくなかったのか、と気づいた。
少なくともあの男がいる状態には戻りたくないのだろう。
「家はほしい」
「俺もそう思う。戸籍も」
「……できれば知り合いとか家族も」
「まあさっきよりは控えめか」
決まりだな、と火原は言った。
こんなにあっさり決まるとは思わなかった。
敦賀はついさっき強引に話を切り上げた自分が少し恥ずかしくなった。火原が何を考えているのか知るのが怖かったのか、あるいは自分の考えを伝えるのが怖かったのか、今となってはよくわからなかった。
火原に腕を掴まれる。
二人で並び立つように琥珀を纏う神と相対した。
「俺たち二人とも移してもらった世界で生きたいんで、家と戸籍をください!あと家族とか知り合いとかもイイ感じに…なんていうか…」
「なんでもいいです。移動でも再現でも」
敦賀は神をまっすぐ見つめた。
ようやく、あるいは不幸にも、自分がなにを一番気にしていたかわかってしまったのだ。
──どうせ『2人で』助かりたいと思ったに決まっているのに。
火原へ思ったことがそのまま自分に返ってきたようだった。
「お願いできますか?」
エメラルド・ラマは、声を発しない。代わりにしなやかな触手の指で静かにフードを下ろした。
青白い顔には凹凸一つなく、ただ琥珀の眼だけがあった。
終幕.
見知らぬ一軒家で目を覚ました。
まず初めに確認したのは敦賀の姿だった。敦賀も同じく火原を探していたのか、視線がかち合った。
そこから家の中と外の景色をざっと見て安全を確認し、家探しに移って驚いた。
自分の部屋がまるごとあった。
隣の部屋には敦賀の部屋があった。
正確には広さや窓の位置が違うので、限りなく精巧な再現といった感じなのだが。
「登記の通知書があった」
敦賀がぺいと書類を投げた。この家の住所や不動産番号のほか、登記名義人として敦賀楽也の名があった。
「僕の家だ」
嬉しいとも不満ともいえない、とりあえず事実の把握に努めている顔だった。
火原は慌てて玄関を飛び出して表札を見た。金属製の立派なプレートに敦賀と刻印されており、その下にテプラで火原と貼られていた。
「なんでだよ!」
「それぞれの家って言わなかったお前の落ち度だな」
あとからやってきた敦賀が先ほどとは打って変わって勝ち誇った表情を浮かべながら、表札の隣にある郵便受けを漁り、パンパンに詰まった『黄金知性会』の勧誘チラシを取り出した。
「さっきあちこち電話したけど一通り繋がったよ。職場もある」
「全部元通りだし家も手に入って完全無欠ってか?」
「さあね」
復元された人間をどう捉えるかだね、とあっけらかんとした声が返ってくる。
「なんかさっぱりしてねぇか?」
「今更ウジウジしてて意味ある?」
「ないよ、ない」
「じゃあご飯にしよう。冷蔵庫に冷凍のビーフモモがあったよ」
「なんだよそれ」
「チベットの餃子」
敦賀はさっさと中へ戻ってしまった。
火原も慌てて新居へ戻った。
カレンダー曰く、3月15日のことだった。
<了>
【背景】
エンドCで世界が滅んだ際、エメラルド・ラマに挑戦者判定された火原(と敦賀)は謎かけを出題され、回答まで別の世界線に預けられることになった。がんばれ!
エメラルド・ラマの設定は新マレモンのほうを参考にしてます(神格編p.212)
【あとがき】
焦土エンドCで成仏できないという話だったので、とりあえずシナリオ一本行ってもらいました。
できるだけ二人の設定や焦土エンドCというのを活かせたらいいなと思いながら書きました。
あと普段は中国語で卓をやってるそうなので中国要素もねじこみました。
完全な二次創作小説ですが、この設定を採用して探索者として復活してもいいです(?)(世界線移動というクソデカ設定付与しておいて…)
詳しいあとがきは後日ふせったーに書かせていただきます!リクエストありがとうございました。
▼skeb受付中!