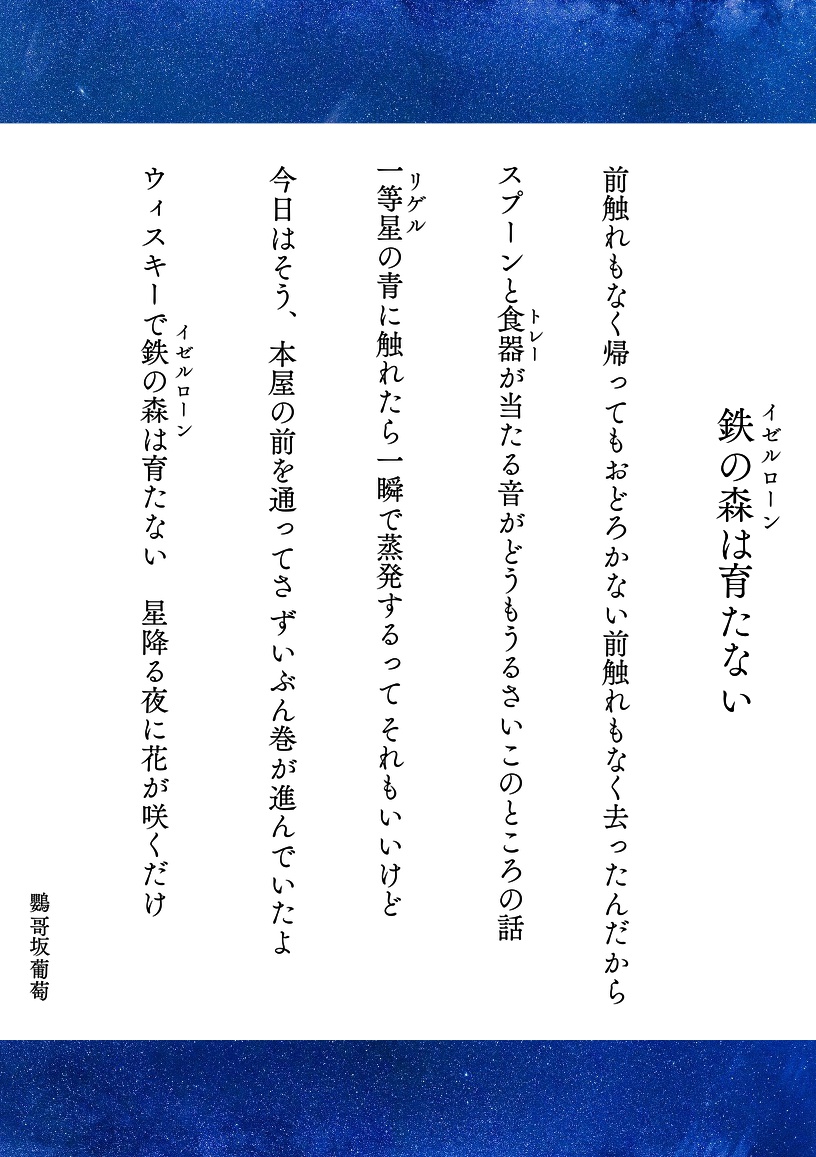街はずれの小高い丘、遠くに海岸線を臨みながら古い小さな洋館があった。くすんだ白い壁とは裏腹に洋館の傍の薔薇の生垣は大層綺麗で、長い年月を感じさせるような、しかし永遠に止まっているかのような、不思議な屋敷だった。男は二階の窓を見上げた。外からは青空が反射して、上品なレースのカーテンがかろうじて見えるくらいだ。男は庭師だった。数年ほど前から薔薇の生垣を任されていた。まだ若く、背は高く、眉がすっと伸びた、精悍な顔立ちの男は、屋敷の主と言葉を交わす唯一の人間だった。主は、名をダグ・ウォーレンと言い、杖をついた白髪の紳士だった。一日の大半を窓辺に座って庭を眺めることに費やしていた。静かで密かな老人が、わざわざ庭師を雇っているのもこれが理由だった。男はドアをノックすることもなく、生垣の傍に鞄を置いて、当たり前のように薔薇の面倒を見始めた。生垣もさほど大きなものではなかったが、二階の窓から楽しむには十分な大きさだった。花の色は赤、白、ピンクの3種類で、生垣全体は男の手によって精密に整えられていた。「宝飾職人が手掛けた薔薇の小箱みたいだ」と主に言われたこともあった。ただ中ほどあたりに一株だけ手つかずの薔薇がある。黄色い薔薇の、小さな株だった。主の老人が言うには、死んだ妻が植えたものだから、なにもしなくてよいとのことだった。無論男はそのとおりにした。雇い主の意志は尊重されるべきであったし、生垣のバランスを考えても、小さな黄色い薔薇はそのか弱さから、邪魔になるような存在でもなかった。日が真上を少し過ぎたころ、男は今日の作業を終えた。報告のために玄関をノックする。ややあってドアが開き、気品と皺が刻まれた顔が覗いた。ダグ・ウォーレンだった。
「お疲れ様。紅茶を飲みなさい」
ウォーレンに促されて男は中に入った。ウォーレンはほの暗い屋敷の中では老人という形容がふさわしかった。
「ありがとうございます。今日はいつもどおりで、特に報告することもございませんが」
「紅茶は休息に使う。報告に使うものじゃない」
老人は優しく微笑んで砂糖入れを渡した。男は砂糖を一杯だけ入れて飲むのだ。
「ここに通うのは大変じゃないかね」
「いいえ、何度も言いますが七日にいっぺんですし、ここまでの道はなだらかですから、平気ですよ。ウォーレンさんこそ買い物が大変では?」
「私も平気だよ。外に出なくてはますます足が悪くなる」
「給仕さんを雇うつもりは?」
「そんな身分じゃないよ」
男は買い物くらいなら自分がしてやってもよかったが、庭師の身でそこまで申し出る気にはならなかった。そもそもこの屋敷の主は、掃除も料理も自力で、それも器用にやる男だった。ウォーレンは男の向かいに座って、自分のカップに口をつけた。男に出されたカップと同じ形のカップだった。
「僕にできることは精々薔薇を切ったりすることぐらいで、まったくお恥ずかしい限りですが、今回もそれを仕事と言い張って帰るとします」
男は空のカップを置いて席を立った。雇い主の老人は穏やかに笑いながら玄関まで彼を見送った。
「君の手前は見事だよ。私はとても好きだ」
別れしな、老人は男の肩を軽く叩いた。男は少し弾んだ声で礼を言った。
「もっと君と居たいよ、でもせっかちだからね」
老人の言葉に男は本当ですかと答えた。
次もその次も特に報告することはなかった。日を追うごとに気温が高くなっており、屋敷までの道が鮮やかになってきている。男はあの静かな老人の、カーテンを閉める姿を思い出していた。半袖のブラウスにボタンをひとつだけあけて、日差しが強いねと言いながらレースのカーテンを引いていた。それから黄色い薔薇を思い出して、暑さで弱らないようにしなければと考えた。
「今日も報告することはございませんで」
男はいつもどおりに雇い主に挨拶をして、そのまま帰路についた。次は七日後。しかし、二日すぎたところで急に気温が上がり、男は七日を待たずして屋敷に向かった。
「ああ」
幸い、薔薇たちはまだ背筋を伸ばしたままだった。不要な蕾を多めに摘み取ったあと、土の様子を見て、水を撒いた。衣服の下を大量の汗が滑り落ちるのを感じて、男は挨拶を取りやめた。二階の窓は相変わらず空が反射して主の様子がわからない。ただ、この時間の二階は暑いから、きっと下の階に居るのだろうと思った。あの階に庭を臨む窓はない。気づいちゃいないだろうと男は屋敷に背を向けた。だがすぐに後ろから声がかかった。
「帰るのか」
「は…」
「君がせっかく時間外労働をしてくれたから、冷たいレモン水を作ったんだ」
男は罰が悪そうに帽子を取って一礼した。
「本当にすまないね」
レモン水を出しながら老人が言った。窓を開けて風が通るようにしているが、暑いな、と男は思っていた。
「君が駆け足で丘を登って来るとき、本当に驚いたよ。別にこれで薔薇がやられたって、私はなにも言うつもりはなかったが、そういうことじゃないか。あれは君の作品だからな」
老人は半袖のブラウスだった。ボタンは一つ開けている。そこから見える首筋に汗が一筋つたった。
「作品と思ったことはないですよ」
男は平静を装ったが、体は冷たいレモン水を素直に喜び、一気に飲み干してしまった。老人がすぐに二杯目を注いだ。男は謝るしかなかった。
「気にしなくていいよ」
「ピッチャーひとつ飲み干してしまうかも」
「それでもいい」
老人はめずらしく声をあげて笑い、男に向き直った。
「むしろ、レモン水でごまかそうと思われるほうが困るな。感謝の気持ちを込めて、ほしいものをなんでもあげるよ。と言ってもここには古びた食器やら花瓶やらしかないし、ごく普通に時間外手当になるだろうとは思うけどね。いくらくらいがいいかな。多少はたくわえがあるからね。買ってほしいものでもいい」
老人はしゃべりながら値打ちのありそうなものをいくつか手に取って、ガラクタだと言いたげに首を振った。男はなんでもですかと聞き直した。
「私のできる範囲ならね」
老人の明るい声が静かに響いた。風がその襟を小さく揺らす。男はグラスを強く握りしめた。
「あなたの身体は」
ベッドは男二人が使うには少々狭かった。老人はシャツのボタンを外していく手を少し怯えた様子で見ていた以外は、おとなしかった。男が自分の服を脱いだあとは簡単だった。
「断るかと思った」
男は身体の下で小さく反応する老人の髪に触りながらつぶやいた。
「なんでもやると約束したから」
ところどころ上ずりながら老人が答える。男が動くと咄嗟に腕を掴んで刺激に耐えるように目をつぶった。
「嫌だと言えばよかったのに」
「白をきれというのか、老人らしく」
汗をにじませながら屋敷の主は庭師を見上げた。怒りがこもったというよりは、悲しんでいるような眼だった。男は困惑した。
「君がほしいと言ったのだろう。せめて満足するまで使いなさい」
「ウォーレンさん……」
老人は目をつむって顔をそむけた。先ほどからずっとこの調子だった。男が顔を近づけて口づけしても離れようとはしなかった。舌を入れても、それを受け入れた。嫌がりはするものの、約束した以上抵抗するつもりはないようだった。
「ウォーレンさん、僕を突き飛ばして、逃げてくれてもいい」
老人はなにも答えなかった。しばらく押し殺した呼吸が続き、すべてが終わりかけた頃には、ほとんど聞こえないほどのすすり泣く声だけになった。
男はなにも期待してなかった。あの日から5日後、つまり本来屋敷に行くはずだった日にまた丘を登った。屋敷に着くや否や追い返されるだろうと思った。薔薇は庭師である彼のおかげでつつがなく花を咲かせていた。だが屋敷は沈黙したままで、彼は仕方なく庭の手入れを始めた。一通り世話をして、ふと、あれのせいで死んでやいないだろうな、と不安になった。手短に道具を片づけて玄関を叩く。挨拶をするつもりはない。ただ、中がどうなっているか確認したいだけだった。
「紅茶を飲んでいきなさい」
彼の雇い主がドアを開け、そう言った。
それからはいつもどおりだった。男は戸惑いながらも薔薇の様子を報告し、老人はうなずきながら砂糖入れを渡した。男は一杯だけ砂糖を入れて紅茶を飲んだ。まるであんなことなど何もなかったかのように、同じ光景が流れていた。唯一、老人の目は、常に怯えと警戒を含んだものになっていた。ずっと悪い。男は思った。俺が考えていたよりずっと悪いことになった。老人は庭師を雇い続けるつもりらしかった。彼にとって、あの出来事を理由に庭師を追い払うことさえ不当であるようだった。男は礼を言って家に帰った。七日後も同じように愛する雇い主と紅茶を飲んだ。違うのは彼の眼だけなのだ。その次の七日後も、その次の七日後も、丘が黄金に染まり始めた七日後もそうだった。
二階の窓に曇り空が反射していたある日、男は普段通り薔薇を美しく整えたあと、数歩だけ歩いて屈んだ。指から外さないでいた鋏がカチ、カチ、と音を立てる。それに伴い男の足元に黄色い花が落ちていく。
「やめろ!」
怒号が走るまでそう時間はかからなかった。ダグ・ウォーレンが玄関から駆けてくる。男は鋏を入れ続けた。ウォーレンが愛していた黄色い薔薇が次々と落ちていった。
「やめろ!それは妻の花だぞ!」
ウォーレンは杖を振り上げて庭師の頭を叩いた。庭師は鋏を置かなかった。
「妻の花から離れろ!きちがいめ!私の薔薇に触るな、妻が植えた薔薇なんだ、お前が触っていいものじゃない!きちがいの若造が!」
ウォーレンは半狂乱で杖を振い続けた。前髪は乱れ、ゼェゼェと呼吸が荒くなる。眼ははっきりと、憎しみと怒りでいっぱいだった。庭師は頭から垂れる血をぬぐいながら静かに言った。
「また咲きますよ」
「うるさい!」
再び杖が飛び男の頭を打った。
「もう来るな、恩知らずの小僧!二度と顔を見せるな!」
老人の金切り声に男は静かに頷いた。鋏を鞄に戻してふらふらと丘をくだった。風は冷たい。そういえば彼はもう長袖になっていたな、と思った。
男が屋敷を去って、いくらかの年月が過ぎた。それは男が屋敷に通い続けた時間より少し長い程だった。男はその日ネクタイを締めて、上着を羽織って丘に向かった。しばらくぶりに見上げた窓には蜘蛛の巣にひびが走っており、反射した青空を引き裂いていた。生垣もすっかり崩れ落ちて、死体のように色がなかった。男は玄関のドアを押した。ドアはきしみながらも簡単に開いた。男が中に入ると、椅子に腰かけた老人が驚いた表情を浮かべた。
「どうも」
男は短く挨拶をした。老人の足元には酒瓶や割れた花瓶、紙くず、コーヒー豆、錆びた指輪などが転がっていた。天井に目をやると埃がぱらぱらと降ってきているのがわかった。
「何の用だ」
老人は立ち上がった拍子で大きくよろけた。男が支えると腕を張って嫌がったが、力はなかった。
「もう大丈夫ですよ。僕がやりますからね」
男は再び老人を座らせた。老人は怪訝そうに男を見上げたが、男は何も言わず台所に立ち、放置された食器を少しずつ洗い始めた。
「なぜなんだ。帰ってくれ。放っておいてくれ」
老人は少しの間呻いていたが、男がなにも答えないとわかって、黙った。
男は食器を片づけると寝室に向かった。ベッドの埃を払い、軽く床を拭いて、いくつかの寝巻を洗濯場に持って行った。浴室ではかるくぬめりを取り、浴槽を丁寧に洗った。休むことなく冷蔵庫の中を見て、使えそうな食べ物を温めた。
テーブルに並べられた料理を見て老人は不安そうに男を見た。
「食べてください」
男の言葉によろよろと口をつける。スープをすくって小さくすすった。ぼさぼさになった口ひげが湿るのが見えた。
老人が食べ終わって少し経つと、男はタオルと着替えを持って再び現れた。体を洗いましょう、と老人を立たせると、老人はいい、いい、と体を引き離そうとした。
「なにもしません。浴室まで腕を貸すだけです。貴方が洗ってる間は僕は浴室の外に居て、貴方が転んだら開けますけど、そうじゃなかったらなにも見ません」
ややあって、やせた身体を丸めて出て来た老人を男は洗い立てのタオルで包んだ。必要最低限のところだけ拭いてやって、あとは老人自身に任せた。着替えの寝巻を渡して自分の見えないところで着替えさせた。
「今日はベッドでゆっくり休んでください」
老人をベッドまで連れて行き、布団をかけてやった。白い顔の老人が言った。
「お前は妻の花を取った」
男は無視してリビングに行き、ソファの埃を払って身をうずめた。一日ではどうにもならない散らかりようだから、掃除だけでも一週間はかかるだろうと思った。彼の世話はもっとかかるだろうとも。
翌日、男はリビングの掃除にかかった。床に転がったものを集めるだけでも相当の時間を要した。壊れた家具も捨てることにした。老人は廊下に立って、彼の後ろ姿を見つめていた。しばらく見つめてたあとは黙って寝室に戻ったが、いつの間にかまた廊下に立っていた。昼になるまでに男が買い物をしてきて、老人にパンと小さなチキンソテーとカボチャのスープを食べさせた。全て食べたことを確認して、男が食器を下げると老人がありがとう、と小さく礼を言った。男は聞こえなかったふりをした。ただ頭の中ではウォーレンさんはどんなになってもウォーレンさんだなと思っていた。それはかなしいことのようでもあった。
リビングの掃除は一日では終わらなかった。男が来て三日目、ようやくゴミの仕分けが終わり、床を磨くことができた。ソファのカバーを取り換えた。老人は足を引きずりながら外までゴミ袋を持って行こうしていた。男に止められて、寝室に行くよう促され、そうか、と不安げな声を出した。
次の日は1階の掃除が全部終わった。とりあえずは昔のように使えるまでにはなった。男は物干し竿を新しく買ってきて、大量に出た洗濯物を一気に干した。風は冷たいが、日が出ていたのは幸いだった。老人は寝室でおとなしくしていた。男が食事に呼ぶと素直に席につき、残さず食べた。今日は「ありがとう」はなかった。ただ思いつめた表情でうなだれていた。男が手を差し出すとそれにつかまり、またベッドへ戻った。
男が来て五日経った。二階を掃除する日だった。あの窓がある部屋は書斎だった。書斎に入るのは初めてだった。古い本とアルバムが今にも崩れそうな本棚にぎっしり詰まっていた。机には埃が厚くなりすぎて何が映っているのかわからない写真が立ててあった。あとは何枚かの手紙らしきものもあった。男はペンを、ランプを、もう用がないであろう全てのものを、淡々と捨てていた。ひび割れた窓は付け替えるよう手配した。老人は追って来なかった。ときおり階下で足音が聞こえるから、気になってはいるのだろう。しかしここまで追って来る気はないようだった。あるいは、足が動かないのかもしれない。
六日目。六日目は、二階の続きと、物を下ろす際にまた少し汚れた一階の廊下を綺麗にした。多少ゆとりのある一日だった。いわしのマリネをパンに挟んで老人に出してやった。相変わらず残さず食べた。埃で咳き込まなくてよくなったリビングで男はひとりごちながら、明日は庭を見ようと考えていた。そのまま夜が更けて男は眠りに落ちた。しかし、すぐ横で足音がして目が覚めた。片足を引きずる独特の足音だった。男が目を開けると、老人が男の体に馬乗りになろうとしていた。驚くほど軽い体を倒しながら老人がぐっと顔を近づける。不安と焦りに満ちた顔だった。寝巻は乱れて鎖骨が露わになっていた。
「手当を……」
「なんですって」
しなだれかかる老人を支えながら男は聞いた。
「時間外、手当だよ。私はなにも払ってないから……でもたくわえは、すべて使ってしまった」
すぐ近くで上ずった声がして男は思わず息を止めた。切迫した、煽情的な声音だった。
「もうこの体ではだめかね……」
老人はぴったりと男に密着した。顔が男の首筋に埋まる。石鹸と老いが混ざった、さびしいにおいがした。
「なにも払わなくていいんですよ」
「だめだ」
「ウォーレンさん」
「あってはならないことだ」
ややあって、再び老人が口を開いた。
「私じゃだめかね。だったら明日、町へ行って、お金を、借りてくるよ。今はもう、ほんとうになにもなくなってしまったから……」
「ああ、そんなこと……」
男が支える手を腰から下へ滑らすと、老人の体が小さく跳ねた。老人は男の首に腕を回し、男は老人に口づけた。前と同じように抵抗しないどころか、老人は自分から舌を絡めて来た。履物をずらし、男の指が中にゆっくり入った瞬間、痩せた腰が思わず浮いた。口づけの最中に吐息が漏れ、男が指を動かす間、それは繰り返された。
「怪我をさせたくないですから、時間をかけますね」
老人は息を乱しながら頷いた。
「満足するまで、好きに……」
余裕のない声を聞きながら男は指を動かし続けた。問題ない具合だと判断したあとは相手の足をかばいながら自身を滑り込ませ、なるべく負担がないように動いた。老人は声を抑えることはなかった。あのときとは違う姿だが、明らかにあのときを覚えている反応だった。
「憐れみで体を重ねたのかね」
事が済んで、男の体に身を預けながら老人が尋ねた。
「前に、貴方が義理で僕と寝たように?」
「ああ」
「貴方は僕の気持ちをわかってない」
男は老人の額に軽くキスをした。そのまま老人を抱えて寝室まで運んだ。その間、老人は身体を小さくして黙っていた。ベッドに横たえられて、男にもう一度キスをされて、初めて少しだけ笑った。
「私は落ちぶれたから……」
老人は消え入るようにそう言った。
夜が明けて、男が来て七日目になった。午前中、男は老人に食器の仕分けを頼んだ。もう使うあてのないものは綺麗さっぱり捨ててしまおうと決めた。老人はようやく自分の役割が回ってきて嬉しそうだった。首筋に男の付けた赤い跡を散らしたまま、けれど気にする様子もなく作業を進めた。男は少しだけ庭を見回った。彼が去ってから一度も手を入れてないようだった。新しい庭師を雇う勇気がなかったのだろう。ダグ・ウォーレンはあの二階から、薔薇たちが死んでいくのを、ただじっと見ているしかなかったのだ。
「午後は気分転換に外に行きましょう」
仕分けがあらかた終わった老人に男はそう告げた。老人は頷いたが、気恥ずかしそうに眼をそらした。男は笑って、着替えを用意してますよ、と隣室から服を持ってきた。そして二人で街へ出かけて、男はウォーレンに新しい服を買ってやった。試着室で密かにキスをした。カフェでコーヒーを飲んだ。杖も新調した。散髪をして、口髭も整えた。丘を登る道は手をつないで歩いた。
「今日で帰りますよ。仕事があるので」
「私のせいだね。お金は……」
「いえ、元々そういうつもりでしたから。仕事が終わったらまた来ますよ」
「いつ来るんだい」
「七日後に」
屋敷の主人に見送られながら男は丘を下った。美しい夕焼けと腐った生垣が対照的だった。
七日後、庭師は大きな白い雲を背に丘を登った。遠くからかすかに届く海風が心地よかった。
二階の窓には晴天が広がっている。庭師は荷物を置いて、鋏を取り出し、朽ちた薔薇の中でも特に外に飛び出てしまっているものを切った。生垣だったものをできるだけ小さくして、一気に解体してしまおうという考えだった。もはや赤も白もなく、ただの黒い塊だった。棘にさえ気を付ければ難なく崩せた。日が真上に来た頃、男は大方の作業を終え、玄関を叩いた。ドアが開き、見慣れた老人が顔を出した。整った白髪と口髭、小奇麗ないでたち、気品を伺わせる笑み。紅茶を差し出す仕草も渡されるカップも、なにもかも昔と同じであった。男は全身が喜びで震えるのを感じた。男が薔薇を見ていた時代から抜け出してきたかのように、老人は屋敷で男を迎えた。ただ一つ違うのは、この老人が男の上で腰を振るようになったということだった。空のカップも片づけないまま、老人と男は情事に耽った。悪い方の足を支えてやるだけで老人は器用に動いた。男が褒めると「うれしい」とだけ答えた。
二人が庭に出たのは日が落ちる時分だった。男は老人の手を引いて生垣の解体を説明した。少し歩き、生垣の中ほどで止まって地面を指さした。小さい株の、弱々しい薔薇が生えていた。黄色い薔薇だ。生垣と無関係に管理していたために完全に腐ることがなかった。今は花はないが、蕾がついているようだった。
「生垣も壊してしまったし、こちらも撤去したいのですが」
男は老人の腰を引き寄せながらそう申し出た。
「君に任せる」
「いいんですか」
「ああ」
老人は薔薇よりも弱々しく笑った。男は眉一つ動かさず老人を見た。
「また咲きますよ」
「いいんだ」
これ以上話したくないとでも言うように老人は男の肩に顔をうずめた。男は老人の額にキスをして家に戻るよう告げた。
庭に一人きりになり、男は土を掘った。薔薇の周りにスコップを入れるたびにブチブチと根が切れる感触がした。何度も何度も土を掘り返し、完全に地面から切り離して、道も海岸線もない、ただの草むらに放り捨てた。屋敷の二階の窓には真っ赤な夕焼けが映っていて、老人がそれを見ていたかどうか、誰にもわからなかった。
おわり